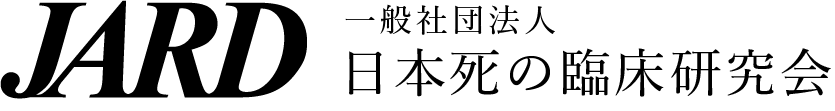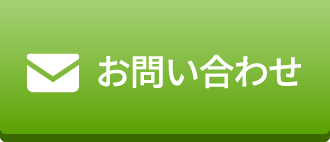委員会一覧
編集委員会
委員長 前澤美代子
会誌「死の臨床」79号(47巻)を2025年6月に発刊しました。本号は、昨年度北海道札幌市で開催されました第47回日本死の臨床研究会年次大会の記録号と投稿論文2編(原著論文1編、調査報告1編)となっております。編集にあたりご協力いただいた、年次大会の事務局の皆様、編集委員および査読委員の皆様に深く感謝申し上げます。
電子ジャーナルが中心となっている状況において、「死の臨床」の冊子について検討をしております。また、論文投稿においては、Editorial Managerのシステムにおいて24時間365日、いつでも投稿いただくことが可能です。編集委員と査読委員ともに、採択まで期間を最短で進むように尽力し、同時にシステムの微調整を行っております。
また、盛岡で開催される第48回日本死の臨床研究会年次大会において、編集委員会主催「さあ、学会発表をしてみよう! 研究超入門編」の交流集会を企画しております。学会発表、研究、論文投稿、文献検索など、はじめの一歩を踏み出せるように、皆様のお役に立てる内容を検討しております。ぜひ、みなさまのご参加ならびに論文投稿をよろしくお願いいたします。
国際交流委員会
委員長 栗原幸江
岩手県盛岡市で開催される第48回年次大会の国際交流広場では、ニュージーランドよりリース・グルート=アルバーツ(Liese Groot-Alberts)氏をお招きして、「ケアに携わる人たちのグリーフケア」をテーマに体験型のワークショップを企画しています。リース氏は、APHN(アジア太平洋緩和ケアネットワーク)で長年にわたりグリーフケアや医療者のレジリエンスに関する講演やワークショップを主催してこられ、2025年にはその功績が認められシンシア・ゴウアワード(Cynthia Goh Award)を受賞されました。また1980年代後半から1990年代にかけてはエリザベス・キューブラー=ロス博士とともに世界各国でワークショップを開催し、グリーフワークやグリーフケアについての先駆的な役割を担ってきた経験もお持ちです。当時3歳のご長女と死別された経験を機に、以来50年にわたりグリーフ・セラピストとして、そして教育者/医療従事者のメンターとしてたくさんの癒しに携わってこられたリース氏の温かな雰囲気に触れるだけでも、そのやすらぎのエネルギーを感じていただけるのではないかと思います。今回は大会長より大きな会場と2時間枠をいただきましたので、多くの会員・非会員のみなさまにご参加いただき、ゆったりとした癒しの輪を広げる場をともに育めたらと願っています。
そして、年次大会翌日の11月3日(月・祝)には東京科学大学にてリース氏のポストカンファレンスワークショップを企画しています。「Healer, Heal Thyself:ケアに携わるわたしたちのグリーフワークとグリーフケア」もまた、「癒し」を身近に感じる体験型のワークショップです(こちらも逐次通訳つき)。リース氏とより近い距離でさらにレジリエンスやコンパッションを養う機会となりますので、どうぞご期待ください。
教育研修委員会
委員長 長澤昌子
2025年度第1回教育研修ワークショップを開催しましたので、ご報告いたします。本ワークショップは1994年より開催し31年目となります。コロナ禍ではオンラインで継続し、昨年より対面開催を再開しました。会場は東邦大学医学部をお借りし、申込者は17名でした。今回は8月9日(土)~8月10日(日)で、交流会を含むトータル13時間30分のプログラムとしました。昨年は1日でしたが、ロールプレイの時間を増やしたことで参加者が自己の課題を明確にしたうえで繰り返し学ぶことができ、学習目標としている「傾聴・観察・確認・共感の基本的な技術や態度を演じる」を達成できた方が多かったです。終了時アンケートでも、小グループのロールプレイでの習熟度が、昨年に比べて特にアップしておりました。参加者からは、「想像以上に満足、たくさんのものをいただいた」「来る前はロールプレイが怖かったが、自分の癖に気がつき、他のロールプレイからも多く学びました」「ファシリテーターのフィードバックがわかりやすく目からウロコがおちました」などの感想がありました。参加前には長時間のワークショップであることに不安を感じていた方もいましたが、学んだ成果を感じられるワークショップとなったと評価しています。
教育研修委員会ではさらに多くの方にご参加いただけるよう、ホームページでの案内や会員に向けてメール通知する他、年次大会内でも委員会企画としてワークショップの内容や学びの効果を伝えてきました。第48回年次大会(11月1日~2日:盛岡)でも、1日目に企画しております。今回、関連学会からの研修案内を通じて本ワークショップに参加した方が複数おりましたので、今後も継続してまいります。さらに、ワークショップ参加が資格更新のためのポイントになることも、積極的に広報していきたいと考えております。
次回は2026年1月24日に、オンラインでのワークショップを予定しております。会員の皆様には、職場で周囲の方々にもお知らせいただけますと幸いです。
企画委員会
委員長 横山幸生
企画委員会では、第48回年次大会(盛岡)におきまして、企画委員会シンポジウム「真の援助者を目指して」を開催いたします。開催にむけて本シンポジウムへ登壇いただく会員を公募いたしました。死の臨床で大切にしている実践や思い、学びや気づきなど会員の皆様からの声を直接聞きたく、毎年シンポジストを募集するようにしています。毎回、「応募があるだろうか?」と不安になりつつも、多くの会員の皆様の「ぜひお話をさせてほしい」という思いに勇気づけられています。公募に参加くださった会員の皆様に心より感謝申し上げます。
シンポジウム当日は、シンポジストにご講演をいただいた後、座長がご講演いただいた内容からテーマを決め、参加くださっているフロアの皆様がグループに分かれてディスカッションを行う時間を設けます。「真の援助者を目指したい」という同じ志をもった参加者でのグループディスカッションを通して、これまでの困難を分かち合ったり、ご自身が勇気づけられたり、新たな気づきを得ることなども多いように感じています。 皆様の本シンポジウムへのご参加をお待ちしております。
ありかた特別委員会
委員長 三枝好幸
ありかた特別委員会では、第48回日本死の臨床研究会年次大会(盛岡)の第1日目、11月1日の午後に委員会企画として、「看取りのケアにおける多職種協働」と題したパネルディスカッションを開催します。概要は以下です。(氏名は敬称略)
【座長】
蘆野吉和(ありかた特別委員会委員・医師・十和田中央病院)
倉持雅代(本部事務局幹事・看護師・青戸訪問看護ステーション)
【パネリスト】
荒和洋(介護支援専門員・居宅介護支援事業所 愛ケアセンター盛岡)
高橋要(介護支援専門員・愛ケアセンター紫波)
萬徳孝子(看護師・岩手医科大学附属病院)
曽場浩代(僧侶・浄土真宗大谷派慈光寺)
看取り期における多職種協働を通して患者さんやご家族にいかにケアを届けられるか、皆様とともに考えたいと思います。多数のご参加をお待ちしています。
年次大会マニュアル改定特別委員会
委員長 三宅 智
日本死の臨床研究会年次大会は、7つの支部が持ち回りで担当し開催しています。各支部を構成する都道府県の数や会員数も異なり、負担が不均等であることも指摘され、また最近では各支部の事務局の運営にも負担が発生している状況でもあります。このような状況を鑑みて、昨年度の年次大会の際に、各支部の年次大会開催の負担を軽減することを目的に、本委員会を立ち上げることになりました。構成メンバーは歴代の年次大会大会長、実行委員長、事務局担当の方々にお願いしています。委員長は関東甲信越支部の三宅が担当し、副委員長は中部支部の西村先生にお願いしました。
これまでに、今年の1月22日、4月1日の2回のZoomによる遠隔会議を開催しました。本部事務局のメンバーにもご参加いただき、これまでの各年次大会開催における問題点や今後の進め方について協議してきました。今年は東北支部、来年は関東甲信越支部、再来年は近畿支部が担当になりますが、再来年の近畿支部大会開催時を目標に年次大会マニュアルを整備する方針で今後も協議を進めていく予定です。これからの年次大会開催が、なるべく無理なく運営出来るようなマニュアル整備を目指していますので、何卒よろしくお願いします。