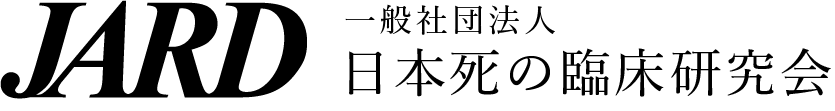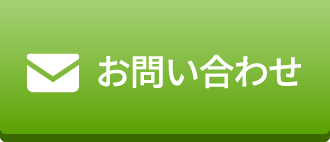本会について
代表理事挨拶

桜町病院 ホスピス科部長
聖ヨハネホスピスケア研究所 所長
三枝好幸(代表理事)
2022年8月、まだ任意団体であった当会の常任世話人会で推薦を受け、10月の世話人会で選出され、11月の総会で承認を受け、世話人代表に就任致しました。2023年1月18日一般社団法人日本死の臨床研究会が設立され、代表理事に就任し、4月1日任意団体が一般社団法人に移行するまで、世話人代表と代表理事を兼任しておりました。当研究会は、1977年12月1日に創設された歴史ある研究会です。偶然ですが2000年を境に23年ずつという節目に、新しく生まれ変わったことになります。
また、私たちをとりまく環境は、「withコロナ」「地震」「豪雨」「豪雪」「酷暑」といった疫病や災害、気候変動に加えて、ロシア・ウクライナ戦争による世界経済への影響など、がん等の病による「死」だけでなはない、より身近な「死」にも向き合うことの必要性を改めて強く感じざるを得ない状況です。
そんな中にあっても、これまで多くの先輩方によって育まれ、大切にされてきた当研究会の「死の臨床における援助の道」は変わることがありません。世の中がどんなんに変化したとしても、痛みや苦しみを抱えている人に向き合おうとするこころのあり方は変わらないからです。
シシリー・ソンダース先生は、「人生の最期に際して患者・家族の苦しみからの解放を優先し、尊厳のもとにケアを提供するために働く人々のこころあり方」を「ケアリングマインド」として示されました。私なりの解釈ですが、これを、「全人的なケアを念頭においた温かくもてなすこころを持って、困難や苦痛を抱えている人と向き合おうとする姿勢」とイメージしました。「こころのあり方」や「姿勢」ですから、ホスピス緩和ケアに留まらない、医療の世界だけでもない、もっと普遍的なものです。だとすれば「ケア」は、痛みや苦しみを抱えている人に対して、いつでも、どこでも、できるということです。
西日本新聞に「お連れ様はどちらですか?」という以下の記事がありました。
『半世紀以上も連れ添った妻に先立たれた、横浜市の知人男性からこんな話を聞いた。男性は葬儀を終えた後、故郷である佐賀県唐津市の寺に納骨するため、羽田空港から空路、九州へと向かった。遺骨を機内に持ち込めることは知っていた。でも入れたバッグがかなり大きく、念のため搭乗手続きの際に中身を伝えた。機内に乗り込み、上の棚にバッグを入れて席に着くと、客室乗務員がやって来てこう言った。「隣の席を空けております。お連れ様はどちらですか?」搭乗手続きで言ったことが機内に伝わっていたのだ。男性が「ああ、上の棚です」と説明すると、乗務員はバッグごと下ろしてシートベルトを締めてくれた。飛行中には「お連れ様の分です」と飲み物も出してくれたという。「最後に2人でいい“旅行”ができた」と男性。その表情を見ていたら、こちらも温かい気持ちになった。』
この客室乗務員の行動から、「ケアリングマインド」を持ち続けることの大切さを改めて学ぶことができます。
医療職、宗教職、社会・心理職、一般教育職、他の研究職、さらには一般市民まで、職種の垣根を越えてマインドの普遍性を共有し、死の臨床における援助の道を探求・研究し、学び、実践して、述べ伝えるという研究会の使命を、皆さんと共に果たしていきたいと思います。
それから、コロナ禍にあってもう一点大きな変革を余儀なくされたのが年次大会の開催形式です。2020年は年次大会が開催されず延期、2021年は完全Web開催、2022年はハイブリッド開催でした。本研究会は、「あたたかさ」や「おもてなし」の心を大切にし、大会参加者に感じていただく中で、多様な職種、市民が学び、思いを共有し、経験を相互伝達できる場所、日々奮闘する多くの会員にとっての「居場所」や「よりどころ」でありたい、と考えております。遠方までいかなくても気軽に参加できるというWeb配信の利点も考慮しつつ、現地に集まるからこそ伝えられるぬくもりや、来てよかったと思えることをより大切にしていきたいと考えています。また、委員会活動や支部会活動も同様に活動に変化はありましたが、時代に即しつつ、向かうべき方向性は変わりません。
私はまだ学生であった1982年に柏木哲夫先生のご著書「死にゆく人々のケア」を読む機会があり、外科医になるためにホスピス緩和ケアについて学び始めました。当時はがん告知もままならない社会であり、自院で手術した患者さんは、最期まで自院で診ていましたが、残念ながら苦痛緩和も不十分で患者さんの人としての尊厳も守られているとはいえない状態でした。自分が手術した患者さんが再発して戻ってくるならば最期まできちんと診て差し上げられるように、終末期のケアを学ぶことは外科医として当然のことと考えていました。1998年からホスピス専任となり25年が過ぎましたが、死の臨床においてケアが必要であることはかなり広まったものの、知識や技術を伝えることに比べ、マインドはなかなか伝えられていないと感じます。
今後とも、会員の皆様と共に歩み、当研究会と皆様の発展に尽力できますよう、決意を新たにしております。皆様のご理解とご協力を切にお願い申し上げます。
定款・規定
年次大会の歴史
| 回数 | 開催年月日 | 開催場所 | 年次大会長(世話人・研究会長)* |
|---|---|---|---|
| 1 | 1977(昭52).12.11 | 大阪 | 河野博臣 |
| 2 | 1978(昭53).11.26 | 東京 | 河野友信 |
| 3 | 1979(昭54).12. 2 | 神戸 | 金子仁郎、河野博臣、隅寛二 |
| 4 | 1980(昭55).11.30 | 大阪 | 岡安大仁、桂戴作、季羽倭文子 |
| 5 | 1981(昭56).11.29 | 大阪 | 柏木哲夫 |
| 6 | 1982(昭57).11.14 | 東京 | 篠田知璋 |
| 7 | 1983(昭58).11.27 | 京都 | 前川暢夫 |
| 8 | 1984(昭59).11.24-25 | 東京 | 水口公信、小松玲子** |
| 9 | 1985(昭60).12.7-8 | 京都 | 福間誠之、河内恵美子 |
| 10 | 1986(昭61).11.29-30 | 東京 | 芳賀敏彦、渡会丹和子 |
| 11 | 1987(昭62).11.28-29 | 浜松 | 原義雄、長屋好美 |
| 12 | 1988(昭63).12.3-4 | 神戸 | 隅寛二、藤腹明子 |
| 13 | 1989(平 1).11.25-26 | 東京 | 季羽倭文子、アルフォンス・デーケン |
| 14 | 1990(平 2).10.13-14 | 札幌 | 方波見康雄、峯岡智恵 |
| 15 | 1991(平 3).12.7-8 | 大阪 | 辻悟、林 治子 |
| 16 | 1992(平 4).10.17-18 | 福岡 | 藤江良郎、阿蘇品スミ子 |
| 17 | 1993(平 5).11.20-21 | 東京 | 小島操子、山崎章郎 |
| 18 | 1994(平 6).11.5-6 | 長岡 | 田宮仁、金子ノリ |
| 19 | 1995(平 7).11.18-19 | 京都 | 西森三保子、中木高夫 |
| 20 | 1996(平 8).11.23-24 | 東京 | 佐藤禮子、松岡寿夫 |
| 21 | 1997(平 9).11.8-9 | 名古屋 | 渡辺正、馬場昌子 |
| 22 | 1998(平10).11.7-8 | 佐賀 | 柿川房子、三木浩司 |
| 23 | 1999(平11).9.17-18 | 札幌 | 形浦昭克、皆川智子 |
| 24 | 2000(平12).11.11-12 | 広島 | 本家好文、鈴木正子 |
| 25 | 2001(平13).11.17-18 | 仙台 | 山室誠、清水千世 |
| 26 | 2002(平14).11.23-24 | 高崎 | 斎藤龍生、渡辺孝子 |
| 27 | 2003(平15).11.15-16 | 徳島 | 寺島吉保、原田寛子 |
| 28 | 2004(平16).11.27-28 | つくば | 庄司進一、紙屋克子 |
| 29 | 2005(平17).11.12-13 | 山口 | 末永和之・兼安久恵 |
| 30 | 2006(平18).11.4-5 | 大阪 | 田村恵子、恒藤暁 |
| 31 | 2007(平19).11.10-11 | 熊本 | 井田栄一、尾山タカ子 |
| 32 | 2008(平20)10.4-5 | 札幌 | 藤井義博、菅原邦子 |
| 33 | 2009(平21)11.7-8 | 名古屋 | 佐藤健、安藤詳子 |
| 34 | 2010(平22)11.6-7 | 盛岡 | 蘆野吉和、長澤昌子 |
| 35 | 2011(平成23)10.9-10 | 千葉 | 林章敏、小松浩子 |
| 36 | 2012(平成24)11.3-4 | 京都 | 堀泰祐、若村智子 |
| 37 | 2013(平成25)11.2-3 | 松江 | 安部睦美、石口房子*3 |
| 38 | 2014(平成26)11.1-2 | 別府 | 山岡憲夫、日浦あつ子 |
| 39 | 2015(平成27)10.11-12 | 岐阜 | 西村幸祐、澤井美穂 |
| 40 | 2016(平成28)10.8-9 | 札幌 | 前野宏、門脇睦子 (名誉大会長:石垣靖子)**** |
| 41 | 2017(平成29)10.7-8 | 秋田 | 嘉藤茂、石川千夏 |
| 42 | 2018(平成30)12.8-9 | 新潟 | 三宅智、梅田恵 |
| 43 | 2019(平成31)11.3-4 | 神戸 | 安保博文、松本京子 |
| 44 | 2023年に延期 | 松山 | 中橋 恒、井上実穂 |
| 45 | 2021(令和3)12.4-5 | 福岡 | 小杉寿文、梅野理加 |
| 46 | 2022(令和4)11.26-27 | 津 | 松原貴子、辻川真弓 |
| 44 | 2023(令和5)11.25-26 | 松山 | 中橋 恒、井上美穂 |
| 47 | 2024(令和6)10.12-13 | 札幌 | 田巻知宏、梶原陽子 |
予定
| 回数 | 開催年月日 | 開催場所 | 年次大会長(世話人・研究会長)* |
|---|---|---|---|
| 48 | 2025.11.1-2 | 盛岡 | 木村祐輔、高屋敷麻理子 |
| 49 | 2025.10.31-11.1 | 甲府 | 中村陽一、前澤美代子 |
* 主催する世話人は第10回から「研究会長」、第19回から「年次大会長」 と称することになった。
** 第7回から主催する世話人は男女のペアとなった。
***第37回は異職種のペアとなった。
****第40回の記念大会のため特別に名誉大会長を設けた。
大会プログラム
2010年〜
| No.55(2010年発刊)第33回年次大会(2009年 名古屋)の記録号 | 2010 |
| No.57(2011年発刊)第34回年次大会(2010年 盛岡)の記録号 | 2011 |
| No.59(2012年発刊)第35回年次大会(2011年 千葉)の記録号 | 2012 |
| No.61(2013年発刊)第36回年次大会(2012年 京都)の記録号 | 2013 |
| No.63(2014年発刊)第37回年次大会(2013年 松江)の記録号 | 2014 |
| No.65(2015年発刊)第38回年次大会(2014年 別府)の記録号 | 2015 |
| No.67(2016年発刊)第39回年次大会(2015年 岐阜)の記録号 | 2016 |
| No.69(2017年発刊)第40回年次大会(2016年 札幌)の記録号 | 2017 |
| No.71(2018年発刊)第41回年次大会(2017年 秋田)の記録号 | 2018 |
| No.73(2019年発刊)第42回年次大会(2018年 新潟)の記録号 | 2019 |
| No.75(2020年発刊)第43回年次大会(2020年 神戸)の記録号 | 2020 |
| No.76(2022年発刊)第45回年次大会(2021年 福岡)の記録号 | 2022 |
| No.77(2023年発刊)第46回年次大会(2022年 津)の記録号 | 2023 |
| No.78(2024年発刊)第44回年次大会(2023年 松山)の記録号 | 2024 |
それ以前のもの
| No. | 発行年 | No. | 発行年 | No. | 発行年 | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1978 | 3 | 1980 | 15 | 1990 | 35 | 2000 |
| 2 | 1979 | 4 | 1981 | 17 | 1991 | 37 | 2001 |
| 5 | 1982 | 19 | 1992 | 39 | 2002 | ||
| 6 | 1983 | 21 | 1993 | 41 | 2003 | ||
| 7 | 1984 | 23 | 1994 | 43 | 2004 | ||
| 8 | 1985 | 25 | 1995 | 45 | 2005 | ||
| 9 | 1986 | 27 | 1996 | 47 | 2006 | ||
| 10 | 1987 | 29 | 1997 | 49 | 2007 | ||
| 11 | 1988 | 31 | 1998 | 51 | 2008 | ||
| 13 | 1989 | 33 | 1999 | 53 | 2009 | ||
| 1978〜1979 | 1980〜1989 | 1990〜1999 | 2000〜2009 | ||||
*会誌「死の臨床」は1989年以降は偶数番号は抄録号ですが、2022年度以降は記録号のみとなります。
組織
.pptx.png)
役員
代表理事
三枝好幸
常任理事
池永昌之、石橋あかね、井上実穂、小松万喜子、西村幸祐、平山 功、細谷 治、蛇口真理子、三宅 智、本松裕子、前澤美代子、 吉岡 亮
支部代表理事
田巻知宏、木村祐輔、中村陽一、橋本 淳、白山宏人、足立誠司、下稲葉順一
監事
矢津 剛、岩崎紀久子
代議員
事務局
連絡先
〒187-0012
東京都小平市御幸町131-5 ケアタウン小平内
TEL:042-312-0021
FAX:042-312-0025
事務局長
茅根義和
幹事
倉持雅代、鈴木慈子、大嶋健三郎