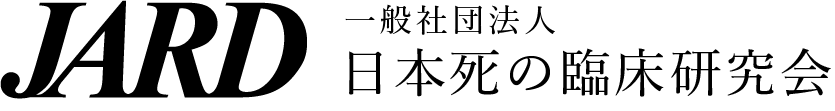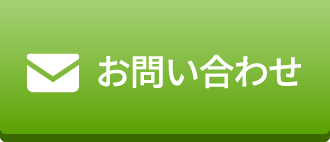委員会一覧
編集委員会
委員長 前澤美代子
編集委員会は、投稿論文の査読を通して洗練された論文の掲載となるよう進めております。また、「死の臨床 79号」の編集作業を行っております。ここ数年の年次大会における事例検討会の「意見交換の内容」の掲載について、参加者の同意を得ていないため掲載への配慮が必要となっています。したがって、事例検討は、事例提供者が抄録を掲載し、事例検討後の感想や学び、新たな気づきなどを加筆して掲載している傾向にあります。さらに、事例報告については倫理審査委員会の承認を得るためのシステムの不足などの課題もあります。それぞれの課題や懸念についてお知らせ頂き、良い方向となるように検討したいと思います。
これまで、論文投稿や演題登録において、筆頭者と共同研究者のすべてが会員であることが求められていました。これを、筆頭者のみ会員であることと変更しました。今後も会員の皆様の論文投稿や年次大会の演題登録を推進していきたいと思います。
国際交流委員会
委員長 栗原幸江
国際交流委員会では、さまざまな文化の背景や価値観、そして実践に触れ、自己のとらえ方や考え方・感じ方が豊かになることを目的として、年次大会において、グリーフケアやセルフケア/スタッフケアを軸にしたテーマで講演会やワークショップ等を企画・開催しています。
岩手県盛岡市で開催される2025年度の年次大会の国際交流広場では、ニュージーランドよりLiese Groot氏を招聘して、「ケアに携わる人たちのグリーフケア」をテーマに体験型のワークショップを企画しています。Liese Groot氏は、APHN (Asia Pacific Hospice Palliative Care Network:アジア太平洋ホスピス緩和ケアネットワーク)の参加国はじめ数々の国で、緩和ケアの教育者および医療従事者のためのコンサルタントとして、喪失・悲嘆・死別等へのケアに関する多くのワークショップやセミナーを重ねてこられた方です。とりわけ介護者のセルフケアに関しては、つながりの中に強さと希望を見出すことに関するトレーニングが著名で、今回も緩和ケアやエンドオブライフケアに携わるスタッフがケアされるひとときになればと願っています。
体験型ワークを媒介として、その場に集う会員・非会員のみなさまとともに学び、語り合い、「感じる・考える・気づく」を大切にする場づくりに向けて委員一同準備を進めています。ご自身の、そしてともに働く仲間のグリーフケアの機会として、またネットワーキングの場として、「国際交流広場」への多くの方々のご参加をお待ちしております。
また、死の臨床研究会国際交流委員会は、APHNとのさらなる協働のために結成されたホスピス緩和ケア国際協力コンソーシアムの一員として、会員のみなさまに関連情報などもお届けしていきます。APHNが隔年開催しているアジア太平洋ホスピス緩和ケアカンファレンス(Asia Pacific Hospice Palliative Care Conference)は、2025年4月23日(水)~26日(土)にマレーシアのサラワク州クチンにて第16回目の開催となります。大会テーマは「多様性を受け入れ、コミュニティをエンパワメントする」(”Embracing Diversity, Empowering Communities”)。緩和ケア分野の世界的なリーダーと交流し、知見を得られる絶好の機会ですので、参加を検討してみてはいかがでしょうか。
教育研修委員会
委員長 長澤昌子
教育研修委員会は年間計画に沿って、年次大会企画と第2回教育研修ワークショップを開催しましたので報告します。
第47回日本死の臨床研究会年次大会の1日目に90分枠で委員会企画を開催しました。テーマは「共に学びましょう『死の臨床に活かすコミュニケーション』ACPの鍵はコミュニケーション~実践!ACPの始め方、進め方~」としました。教育研修ワークショップで学んでいるコミュニケーション技法の要点は「傾聴」「観察」「確認」「共感」です。ACPの場面においてこの技法を活用し、相手の価値観を確認することができれば、患者を主体とした意思決定支援につながることをレクチャーで伝えました。さらに、委員によるロール・プレーを参加者に観察していただくことで、レクチャーで伝えた内容を確認し、実践で活用する場面がイメージできるよう進めました。終了時アンケートにご協力いただいた方からは、「ACPにおけるコミュニケーション能力の大切さを改めて感じた」「ACPをひろめていくのに、コミュニケーションの実践が必要なことが納得できる内容だった」などの感想がありました。会場には300名を超える参加があり、そのうち80%以上が教育研修ワークショップを「知らなかった」や「知っていたが参加したことがない」という方でしたので、当委員会の活動を知っていただく機会になったと考えております。
2024年度第2回教育研修ワークショップを12月21日(土曜日)13時~17時、オンラインで開催しました。参加者16名のうち12名が初めて参加した方でした。その中には、第47回の年次大会企画でワークショップを知り参加した方や、知り合いから勧められて参加したという方が複数おられ、大変うれしいことでした。今回も、ミニレクチャー、デモ・ロール・プレー、参加者によるロール・プレーというプログラムで進めました。参加者から良かった点として、「普段のコミュニケーションを第三者に観察してもらえたことで、自分のブロッキングの傾向を知ることができた」「具体的な改善策をファシリテーターに教えてもらえた」「患者役をすることで、患者の気持ちを深く考え今まで見えなかったことが見えたと思えた」などの回答がありました。一方、進行スピードが速いと感じた方がいましたので、今後の課題とします。全体として、「死の臨床におけるコミュニケーションについての理解が深まった」「明日からの臨床に活かすヒントが得られた」との回答であり、本ワークショップの目標に近づいていると評価します。
次回は、3月8日にアドバンスコースを予定しております。過去に2回以上参加したことがある方で、更なるスキルアップを目指す方が対象です。参加をお待ちしております。
企画委員会
委員長 横山幸生
2024年10月13日、札幌で開催されました第47回年次大会において、企画委員会シンポジウム「真の援助者を目指して」を開催しました。会場には椅子に座れない方がいらっしゃるほどの多くの方々が集まってくださり、活気のある会となりました。
シンポジウムでは、萩谷翔太様(静岡県立静岡がんセンター)が「Cureに限界はあってもCareに限界はない」、林良彦様(フリーランス緩和ケア医師)が「私が歩んだコミュニケーション研修の過程と臨床応用」、武田ひろみ様(名古屋市立大学医学部附属西部医療センター)が「患者との距離感を大切に」と、興味深いテーマでご講演くださいました。3名のシンポジストが、日々の実践の中で大切にしている患者さんとの向き合い方、ケアへの考えや思いなどを率直に語ってくださり、聴講いただいたみなさまも3人のお話に共感し、気づきをいただきながら、自分自身のケアを振り返る機会になったように感じています。
お一人おひとりのご講演を聞いた後、フロアではお隣同士の3名程度でディスカッションを行いました。初めて出会う参加者同士での語らいでは、死の臨床に真摯に向き合う人々が全国各地で活動していることを知り、同じ思いをもった仲間がいることに勇気づけられた方々も多いのではないかと考えました。
この企画委員会シンポジウムは、第48回年次大会(盛岡)でも開催します。登壇いただくシンポジストは毎年公募をしております。公募のご案内はホームページや会員メーリングリスト等で行う予定です。ご自身の実践や死の臨床への思いなどを、みなさまにぜひ伝えたいと考える会員のみなさまからの応募を心よりお待ちしております。
ありかた特別委員会
委員長 三枝好幸
これまで、多職種協働や連携を通して研究会のあり方を考える、3回シリーズのパネルディスカッションを開催してきました。今後これらを活かしていくための活動や広報を広めていく予定です。また、研究会の活動、特に支部活動の運営のあり方や、これからの研究会を担う若い人たちの育成など、議論を深めていく予定です。
今後とも、会員の皆様にとってより身近な存在となれる研究会を目指し活動していきたいと考えています。